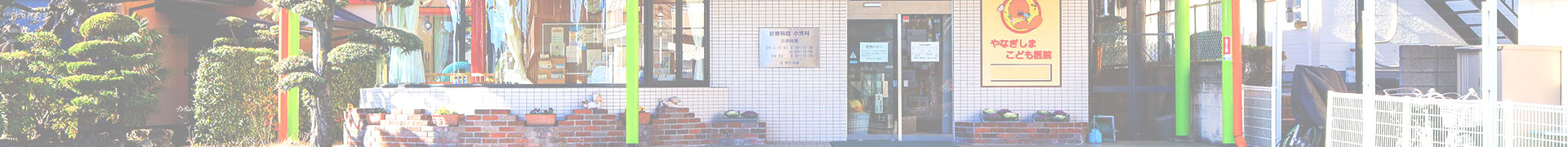
食物アレルギー
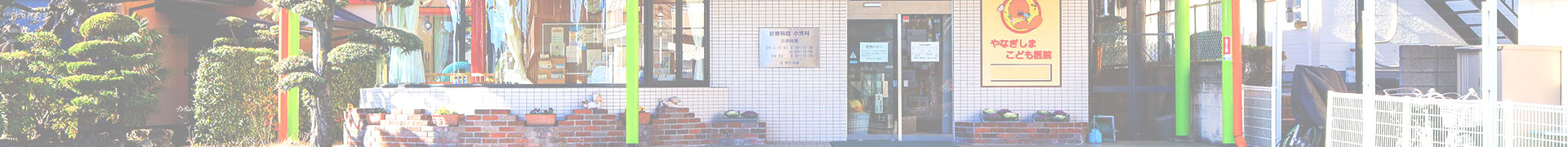
食物アレルギー

食物アレルギーは、卵・牛乳・小麦など特定の食品を食べると免疫系の過剰反応によって、じんましんや湿疹、嘔吐、下痢、咳・ゼーゼーなどの症状を起こす疾患です。症状の程度は軽症から重症まで人によって様々ですが、2つ以上の臓器で症状が出る「アナフィラキシー」を起こすと、重症化の可能性のある危険な状態(アナフィラキシーショック)になることもあります。
食物アレルギーは小児から成人まで認められますが、その大部分は乳児期に発症し、小児期に年齢の経過とともに耐性を獲得して、自然寛解していくケースがほとんどです。アレルゲンとしては、乳児期から幼児期にかけては、鶏卵、牛乳、小麦、大豆に反応することが多く、成長するにつれてエビやカニ、そば、落花生、果物類などが増えてきます。大人になってからはじめて発症する成人型の食物アレルギーは、アレルゲンとして小麦、果物、野菜が多く、耐性は獲得しにくくなります。そのため、原因食品の継続的な除去が必要なことが多いと考えられています。
摂取するアレルゲン量や年齢によっても症状の出現の仕方が異なります。授乳期には発赤疹・湿疹などが現れることが多く、その後、離乳期から小児期にはじんましんや湿疹などの皮膚症状に加え、眼粘膜症状、鼻症状、消化器症状、下気道症状などが現れることが多くなります。
これらの症状が1つだけ現れる場合もあれば、急に複数の臓器に症状が現われるアナフィラキシーをきたすこともあります。アナフィラキシーでさらに血圧低下や意識障害などが急速に起こり、全身の症状が進行する場合を「アナフィラキシーショック」と呼び、生命の危険にまで及ぶこともあります。
食物依存性運動誘発アナフィラキシーは、小学校高学年から中学・高校生に稀に起こる特殊な症状です。特定の食物を食べただけでは症状は起こらず、摂食後(30分~4時間後)に運動をすると、吐き気や嘔吐、じんましん、呼吸困難、めまいなど、アナフィラキシーの症状が現われるのが特徴です。ただし、特定の食物と運動の組み合わせで必ず生じるわけではなく、生活環境や体調の変化、ストレスなどが関与すると考えられています。
特定の果物や野菜などを食べると口唇や口腔内の腫れ、のどの痛みや違和感などが生じる病気です。症状が現われても、多くは食後しばらくすると自然に軽快します。果物や生野菜に含まれるアレルゲンが口腔内粘膜に触れて起こる反応で、近年、幼児・学童・成人での報告が増えています。原因食物としては果物(キウイ、メロン、モモ、パイナップル、リンゴなど)や野菜です。花粉症との関連性も考えられています。
食物アレルギーは症状や重症度に個人差があり、原因となる食物アレルゲンも人によって異なります。食べた直後に明らかな症状(じんましんやアナフィラキシーを起こしたなど)がある場合は原因がすぐにわかりますが、中にはゆっくり現れる遅延型の反応であったり、血液検査で陰性であったりすることもあり、すぐに原因を特定できないこともあります。
診断では血液検査や皮膚テストがアレルギーの原因物質の特定に役立ちますが、血液検査が陽性になったからといって、必ずしも食事制限が必要なほどの症状が出るとは限りません。逆に陰性が出たからといって必ずしも食べて安全ということでもなく、症状が出る場合もあります。
原因食物を特定し、正しく診断を行うためには血液検査や皮膚テストとともに、食物負荷試験が必要となります。食物負荷試験は、アレルギーが疑われる食物を実際に少量ずつ摂取して症状を観察する試験です。
食物アレルギーの治療は、正しい診断に基づいて最小限の食物除去を正確に行い、安全を確保しながら必要な栄養を摂取していくことが基本となります。アレルゲンがどのような食品に入っているのかということや、除去した食物に代わり得る食品についても指導します。
食物アレルギーの多くを占める即時型食物アレルギーの症状は、食物摂取後から2時間以内に出現するケースがほとんどです。どの程度のアレルゲンをとったかアナフィラキシーの既往があるかなどにもよりますが、基本的にはそれぞれの臓器について症状の程度に合わせた治療を行います。じんましんやかゆみに対しては、抗ヒスタミン薬、咳や喘鳴(ゼーゼー・ヒューヒュー)に対しては、気管支拡張薬の吸入などを行います。症状が重篤で、全身に及び急速に進行するアナフィラキシーを起こす可能性がある場合には、自分で治療薬(アドレナリン)を注射することができるアドレナリン自己注射薬(エピペン®)の処方を受けることができます。